crumiiが目指す、SRHR(性と生殖に関する健康と権利)ってなに?
crumiiが目指す、SRHRってなに?
生理や妊娠、避妊、不妊治療、中絶――
私たち女性は生涯を通じて、さまざまな体の悩みに向き合います。けれど、その悩みの解決のためにどのくらいの人がアクションを起こせているでしょうか?
crumiiでは、「SRHR(性と生殖に関する健康と権利)」という考え方を大切にしています。自分の体について正しい情報を得て、必要な医療やサポートに繋がれる環境づくりは、女性が生涯を通じて自分らしく生きるうえで欠かせません。
しかし日本では、まだ十分にSRHRという考えが浸透しておらず、制度や医療アクセスが不十分な面があるため、望まない妊娠や適切な治療を受けられないケースが発生しがちです。
crumiiのチームは、SRHRの普及・実現のためにできました。本記事では、SRHRの基本や日本の現状、そして女性の味方になってくれる産婦人科や専門家とのつながり方を紹介します。
SRHRは、あらゆるライフステージの女性に関わる
「SRHR」とは何の略?
SRHRとは、Sexual and Reproductive Health and Rights(性と生殖に関する健康と権利)のことを指し、WHO(世界保健機関)などが提唱しています。すべての人が自分の体に関する意思決定を行う権利を尊重され、必要な医療や情報にアクセスできることが大切だという考え方です。
SRHRには具体的に、妊娠・出産、避妊、不妊治療、性感染症の予防に加え、子宮頸がんの予防、中絶の選択肢なども含まれています。
「からだの自己決定権」ってどういう意味?
「からだの自己決定権」とは、健康や性的な行為、妊娠・避妊など、自分の体に関して自分の意思で選択する権利のことです。たとえば「避妊方法をどうするか」「妊娠を続けるかどうか」「どんな治療法を選ぶか」などを、本人が主体的に決められるという考え方です。厚生労働省も、この権利を守るために、女性を含むすべての人が自分の体と健康に関して主体的に選択できる環境づくりを推進しています。
ただ、海外に比べると、日本では依然として「性の話題」に対するタブー感が根強く、SRHRの認知や性教育の普及度合いは十分とは言えません。その結果、自分の体を守るための知識が不足することで必要な医療にアクセスできないといった課題があります。
また、中絶については法律上の制限や社会的な偏見によって、妊娠を継続できない事情を抱えた女性が孤立しがちな現状も指摘されています。この点については、改めて別記事で詳しく解説します。
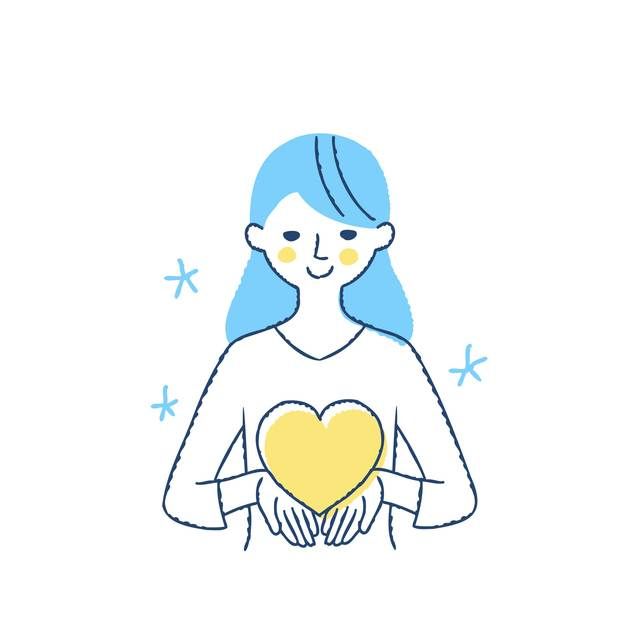
SRHRにはどんな内容が含まれるの?
SRHRには、以下のような内容が含まれます。
生理・PMS(月経前症候群)
症状の緩和や治療について、適切な情報やサポートを得る権利。
妊娠・出産
妊娠する・しないを選択する自由や、出産方法(自然分娩・無痛分娩など)を選ぶ権利。
避妊
ピルや子宮内避妊具(IUD)、コンドームなどの情報と手段を得る権利。どの方法を選ぶかは本人の意思に委ねられます。
中絶
妊娠を継続しない選択ができる権利のこと。また、原則自己負担になっているなど課題はあるものの、日本では「母体保護法(※4)」などによって条件が定められています。
安全な医療を受けられず、不適切な環境で中絶が行われると、女性の体に大きなリスクが伴います。WHOも「安全な中絶へのアクセスは、女性の健康と命を守るために重要な権利である」と提唱しています。
不妊治療
適切な不妊治療へのアクセス、経済的負担を軽減する助成や適切なカウンセリングなどを受ける権利。
性感染症の予防・治療
検査や治療、予防策に関する情報や医療を得られる権利。
※注釈 母体保護法(昭和23年法律第156号)
日本で中絶に関して規定している法律。経済的理由や健康上の理由など、一定の条件を満たす場合に手術を認めると定められている。
自分の体を知り、声をあげる大切さ
SRHRの実現には、何よりもまず自分自身が情報を得て、主体的に声をあげ、アクションすることが大切であると、crumiiは考えています。
まずは、SRHRのプロバイダーである産婦人科医が、女性の味方であることを理解してもらい、適切な情報の発信が必要と考え、メディアの創設にいたりました。その他にも、女性が自分自身でできることもあります。例えば、以下のようなことです。
1.医療機関への受診や相談をする
妊娠の有無や生理不順、強い生理痛など、自分の体のことで気になる症状があれば早めに婦人科を受診しましょう。中絶を考える場合も、正確な情報と適切な医療を受けられるよう、専門家に相談することが大切です。(そのためには、女性の決断を尊重してくれる産婦人科医との出会いがとても重要)
2.正確な情報を収集する
crumiiをはじめ、厚生労働省やWHO、日本産科婦人科学会など公的機関や専門家の信頼できる情報を確認することが大切。SNSをはじめとしたネット上には誤った情報も多いため、情報源の信頼性を確かめる習慣を身につけましょう。crumiiは難しくなりがちなこれらの公的機関の情報を、フラットな目線でわかりやすく解説していきます。
3.パートナーや周囲と話し合う、その環境を普段からつくる
避妊や妊娠、中絶に関する選択は、一人だけで決断しなければならないこともありますが、パートナーや家族、友人など周囲と話し合うことで支援を得られることも多いです。特に、精神面では理解ある話し相手がいるだけで全然違います。普段から相談しやすい環境やコミュニケーションを整えておくことも大切です。
4.自治体やNPOの相談窓口を活用する
自治体が運営する保健センターやNPO法人の無料相談窓口など、専門家に相談できる機会も増えています。判断に迷ったり不安があったりする場合は、積極的に利用してみましょう。
自分らしい選択をするためにできること
SRHRは、すべての女性が自分らしく、安心して人生を歩むためのベースとなります。まずは自分で、「私の体と心は私のもので、大切にすべきものだ」という意識をもつことから。
1.自分の体と心を優先する
生理痛や体調不良など、「これくらい我慢できる」と思わずに、早めに専門家の意見を聞くこと。避妊や中絶などの選択に迷ったときも、世間体や周りの意見に流されず、自分の体と気持ちを大切にしてください。
2.知識を身につけ、情報を更新し続ける
•SRHRやからだの自己決定権、もちろん医療に関する情報も日々アップデートされます。公的機関や専門家が提供する最新の資料を定期的に確認すると安心です。
3.声をあげる勇気を持つ
日本では性に関する話題はタブー視されがちですが、「これってどうなんだろう?」と感じたときに質問や相談をすることで、誤解や不安を解消するきっかけになります。crumiiはこのような場づくりにも寄与していきたいと考えています。
医師に遠慮なく質問する、パートナーや家族と話し合うなど、小さなステップから始めてみましょう。
4.社会全体でオープンに議論できる環境づくり
crumiiが将来的に目指す姿です。学校や職場、メディアなど、さまざまな場でSRHRに関する情報共有や議論を行うことで、正しい知識が広がり、安心して選択ができる社会が実現しやすくなります。
【主な参考文献・参照先】
•WHO(世界保健機関)「Sexual and Reproductive Health and Rights」







